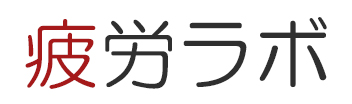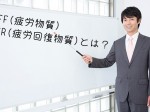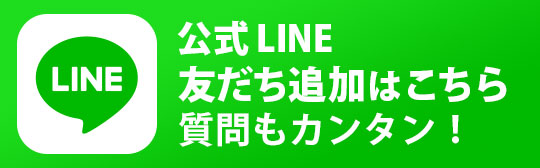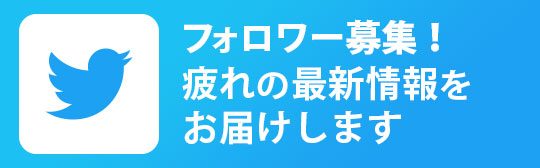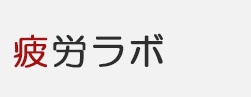温度・湿度・体感温度・不快指数・・・実は快適に過ごすにはこれらの数値を気にすることが重要でした。
ただ気温が高いから暑い、気温が低いから寒いという単純なことではなく、湿度によって快適な空間に変化させることも可能なのです。
- 体感温度を下げて快適な生活を送るには湿度がポイントだった。
- 不快指数が高くなるとジメジメを感じやすく過ごしにくくなってしまう。
- 湿度と温度を適切に保つと夏のジメジメや冬のカラカラを改善することができる。
Contents
湿度で体感温度は変わるのか?体温調節と湿度の関係
夏場の暑い時期は気温が高く、冬場の寒い時期は気温が低くなります。これによって私たちは暑い、寒いといった感覚を得ているのですが、暖かいはずなのになんだか肌寒い、もしくは涼しいはずなのに蒸し暑いと感じることはありませんか?これには体感温度が関係しています。
体感温度とはいったいなんなのか??
体感温度とは人が感じているだろう温度差を数値化したものです。体感温度に一番大きく影響するのが気温ですが、これにプラスして湿度や風速などの影響を受けます。湿度に着目した体感温度の計算方法をミスナール法と呼びます。
温度と湿度のバランスによって体感温度が大きく変わる
日本は夏の場合は高温多湿、冬は低温低湿と言われます。夏はジメジメしていて暑く、冬は乾燥していて寒いという気候です。ジメジメしていたり、乾燥していたりするのは湿度が影響しているからで、高温低湿、低温高湿であれば過ごしやすくなります。
例えば夏の場合
気温30℃・湿度80%→湿度が高く蒸し暑いので不快に感じる
気温30℃・湿度50%→湿度が低いので快適に感じる
となります。同じ気温でも湿度が違うだけで体感温度は大きく変わるのです。
また冬の場合
気温15℃・湿度25%→寒く感じて体が冷える
気温15℃・湿度60%→寒いけれどもなんとなく暖かく感じる
となります。気温と湿度のバランスによって快適に感じるのか不快に感じるのかが変わることを体感することが出来ます。
ですから湿度が高いときは除湿をして湿度が低い時は加湿をすることで同じ気温でも快適な空間を作ることができるようになります。

夏場の不快指数は湿度が高いと高くなる?
梅雨時期から夏場になるとニュースのお天気コーナーなどで不快指数という言葉を聞くことはないでしょうか?
蒸し暑さを数値化したものが不快指数
不快指数とは1957年にアメリカ合衆国で考案され、簡単に言うと蒸し暑さを数値化したもので気温と湿度によって算出することが出来ます。気温や湿度と関係しているのであれば体感温度とは違うの?と思う人もいるでしょう。
実は、不快指数を算出する計算式には風速は含まれておらず、気温と湿度によって算出されます。体感には個人差があるので不快指数は必ず体感と比例しているわけではないことから体感温度と不快指数は別物として考えてよいでしょう。ではなぜ不快指数が天気予報などで取り上げられるのか?ですが、不快指数は一つの指標にすることができるからです。
過ごしやすい不快指数の数値はどのくらい?
体感と比例するわけではないのが不快指数ですが、室内のエアコンを入れるかどうかなどの指標にすることが出来ます。不快指数は数値が低ければ低いほど体感的には寒く、数値が高ければ高いほど体感的には蒸し暑いと感じるので、不快指数がちょうど半分のあたりである60前後であれば過ごしやすい数値となり、75を超えたあたりから多くの人が不快感を示すようになります。生活環境を整える指標とする時に便利に使うことができる数値です。
適切な湿度と温度の保ち方
暑い夏場になるとついついエアコンの温度を下げてしまうのですが、室内をエアコンでキンキンに冷やさなくても湿度を下げるだけで快適に過ごすことが出来ます。現代の日本の住宅は高気密高断熱の住宅が増えているので室内の気温や湿度を快適に保ちやすくなっています。
室内の湿度は40%から60%を目安に
快適に感じる湿度は気温により多少違ってきますが、40%から60%くらいで保つのが良いと言われています。エアコンの除湿機能を上手く使って室内の湿度を下げる工夫をするのですが、40%を下回ると乾燥を感じるようになり、風邪などのウイルスなども活動しやすくなってしまうので注意が必要ですし、反対に60%を上回るとカビやダニなどが発生しやすい環境になってしまいます。
気温に比べて湿度は肌の感覚で計るのは難しいので湿度計を室内において適切な湿度管理ができるようにしましょう。