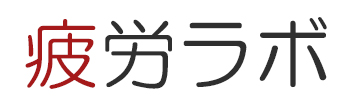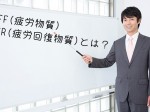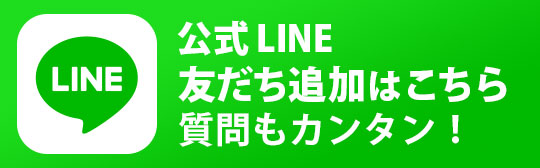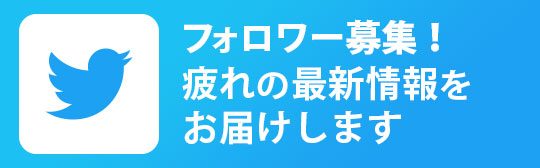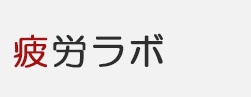多くの人が夏は気温や湿度が高く汗をかきやすく、冷房に当たることが多いことから夏バテをしやすく疲れやすいとイメージしています。
しかし、実際には夏と冬ではどちらが疲れやすいのでしょうか。
- 暑い夏に起こる夏バテが夏は疲れやすいというイメージを作り出している
- 夏ばかりが疲れやすいと思われがちだが実は夏も冬も同じ様に疲れる
- 同じ様に疲れる夏と冬では冬の疲れの方が自覚しにくく危険性が高い
Contents
夏バテ=疲れというイメージから夏の方が疲れやすいとイメージされている
暑い・汗をかく=疲れる?
猛暑と聞くと夏バテをイメージする人も多いのではないでしょうか。気温や湿度が上がることで過ごしにくい日が続くと食欲が減退したり体力が低下したりすることで夏バテが起こります。毎年夏になると必ず夏バテを起こし、夏になると痩せてしまうという人も存在します。

暑いことで疲労が溜まり、夏バテを起こすと考えると夏は疲労が蓄積しやすいと考えることが出来るのですが、中には冬の方が疲れやすいという人も存在します。そもそも夏の疲れと冬の疲れは違うものなのでしょうか。
夏の疲れと冬の疲れのメカニズムは変わらない!
夏ばかりが疲れやすいわけではなかった
夏は汗をかきやすいことから疲れやすいと感じるのですが、汗をかくことが直接疲労に繋がるわけではなく、体温調節の為に自律神経が働き続けることによって疲労が生まれてしまうのです。冷房の効いた室内とそうでない室外を行き来することで気温差が激しくなり一定の体温を維持する為に夏自律神経は活発に働きます。
つまり自律神経が働き続けることで自律神経の機能自体が低下して疲労の根本的な要因となってしまいます。つまり冬でも激しい温度差が生じてしまえば夏と冬では疲れやすさに違いはなくなります。よって夏と冬の疲れのメカニズムは同じなのです。
夏が疲れやすく感じる原因とは
夏は汗をかくことで体の水分が不足したり、暑いことで血管が膨張することによって血圧が低下し倦怠感を感じることから疲れを感じやすい季節になります。

危険度が高いのは夏の疲れよりも冬の疲れ!
夏と冬では疲れのメカニズムに違いはないのですが、疲れを感じやすいのは夏なのに対して二つを比べた時に危険なのは冬の疲れです。冬場の疲れは夏場に比べて自覚しにくいのに危険は冬場の疲れの方が多いのはなぜなのでしょうか。
実は夏の疲れよりも冬の疲れの方が危険だった

夏の疲れは水分が不足したり血管が膨張することによって血圧が低下することで疲れを感じやすくなるのですが、冬の疲れは逆であり寒さを感じることによって血管が収縮すると血圧が上がってしまいます。これは暖かい所と寒い所の気温の差が激しければ激しいほど危険であり、体温調節の為に自律神経が活発になり自律神経自体が疲れてしまいます。
そして、自律神経は血圧の調整をする役目があるので、疲労で機脳が低下してしまい上手く動くことが出来ないと血圧の上昇を止めることが出来ずに血管が破裂してしまう脳卒中などの危険性が高まります。冬場の脳卒中が多いのはこういった理由があるからです。血圧が低いことに対してはあまり危険視されないのですが、血圧が高いことに関しては何かと不安があるので高齢者などは特に急激な血圧の上昇を防ぐ為に温度差を出来るだけ作らない様な住まい作りが重要になります。