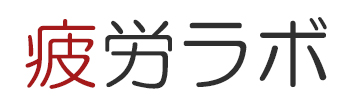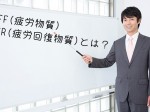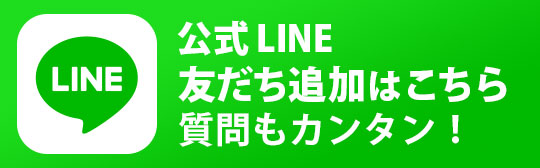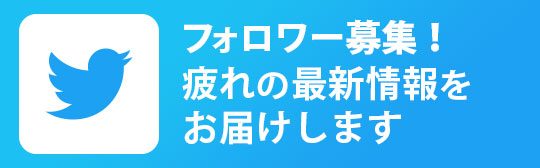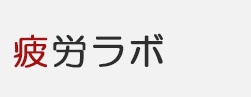暑い日が続く中でジュースやアイスクリーム、そうめんなど冷たいものばかりを飲んだり食べたりしているという人もいるのではないでしょうか。
ですが、暑いからと言って冷たいものばかりとっていると身体はどんどん疲れてしまいます。夏の疲れには暑さももちろん関係していますが、冷たいもののとりすぎも原因の一つなのです。
- 冷たいアイスやジュースばかりでは胃腸の動きが悪くなってしまう
- 胃腸の動きが悪くなると腸内環境が悪くなり自律神経まで乱れてしまう
- 冷たいものの食べ過ぎで疲れてしまっているなら腸内環境を整えよう
Contents
冷たいものをとりすぎるとお腹を壊すのは理由があった
冷たいものばかりとりすぎて、なんだかお腹の調子が悪いという人が増えるのが夏です。
冷たいものをとりすぎるとお腹を壊すのはなぜ?
多くの人は経験的に冷たいものを食べすぎると、お腹を壊してしまうと知っているのではないでしょうか。冷たいものをとりすぎるとお腹が痛くなるだけではなく、下痢になってしまうこともあります。冷たいものばかりを食べていると胃腸の動きが悪くなります。胃腸の動きが悪くなると消化不良を起こしてしまうのですが、その反面、便を体外に押し出そうとする腸のぜんどう運動は冷たいものが刺激となり活発になってしまうので、この結果腹痛や下痢を起こしてしまいます。
胃腸が冷えると動きが悪くなり自律神経にも影響する
自律神経は、体温を調節する、内蔵や血管などの働きをコントロールするなど、無意識のうちに私たちの体内の環境を整える役割を持っています。交感神経と副交感神経が上手くバランスを保つことで身体の健康だけではなく心の健康も維持することができるのですが、腸の動きをコントロールしているのも自律神経です。
腸内環境は自律神経に大きく影響する
腸内環境が悪化してしまうと自律神経の負担が高まり、自律神経が乱れてしまいます。腸内の環境が悪化すると自律神経が乱れ、腸の動きをコントロールする自律神経が乱れると腸内環境が悪化するというように、腸内環境と自律神経はお互いに影響し合っていることで悪循環に陥ってしまいます。自律神経が乱れると、疲労に繋がります。
腸内環境を整えると自律神経も整えられる
腸内環境と自律神経がお互いに影響し合っていることで、いったいどちらを改善すればいいのか?と疑問に思う人もいるでしょう。腸内環境と自律神経がお互いに影響し合っていることで生まれる悪循環は、まずは腸内環境を整えて断ち切りましょう。腸内環境を整えることで、自然と自律神経を整えることに繋がります。
腸内環境って何?
腸内環境を整えるためには腸内細菌のバランスを意識しましょう。腸内には約100種類の細菌が約100兆個存在していると言われており、この細菌は善玉菌と悪玉菌、そして日和見菌と呼ばれる3つに分類することができます。善玉菌は腸内環境を整える作用を持ち、悪玉菌は便秘や腹痛、肌荒れを引き起こし、病気の原因になることもあります。日和見菌は腸内の大部分を占める菌で、腸内の環境によって有害になったり無害になったりする菌です。これら3つの菌のバランスによって腸内の環境は大きく変わり、自律神経だけではなく、健康や美容にも影響します。

善玉菌を優勢にすることで腸内環境を整えることができる
腸内環境を整えるために意識しなければならないのが、腸内の善玉菌を増やして優勢にするということです。悪玉菌が優勢になってしまうと腸内細菌の大部分を占める日和見菌が有害な働きをし始めてしまうので、善玉菌を優勢にすることで日和見菌を無害にすることができます。善玉菌を優勢にするためには、ヨーグルトや漬物など善玉菌となる細菌を含む食材を食べて直接善玉菌を摂取するか、オリゴ糖や食物繊維を摂取して既に腸内に存在する善玉菌を増やす方法があります。善玉菌を優勢にして腸内環境と自律神経の乱れを整え、疲労の予防を心掛けてみましょう。